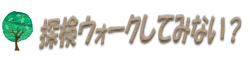浮世絵の展示で有名な太田記念美術館は、原宿駅から歩いてほどない場所にある。
なんとなくミスマッチな感じもするが、今も昔も最先端の文化に触れる場とすれば一番ふさわしい場所なのかもしれない。
7/2から「 青のある暮らし ―着物・器・雑貨」が開催されることを知り、早速出かけることにした。
展覧会の詳しいコンセプトは、公式サイトの説明をご覧いただければと思うが、もともと江戸の人々の間で浸透していた藍染め文化の土壌に、1700年初頭にベルリンで偶然発見された青い顔料が時を経て100年後の江戸で広まった。
ベルリンブルー(ヒロシゲブルーとも呼ばれている)による美しいグラデーションの表現が深まり、浮世絵の大きな転換点ともなった。
そんな絵画としての「青」の変遷や、江戸っ子が愛した暮らしに浸透した青の文化を、浮世絵を通じて感じ取ってほしいという企画である。
太田記念美術館の展示は1階と2階に分かれている。
まずは1階、2階に続く階段を囲むようにぐるりと壁沿いに展示されている作品を順番に鑑賞していく。

歌川国貞 今様三十二相 すゞしさう 安政6年(1859)2月
季節は7月ということもあり、夏の風景、庶民の浴衣姿が多く登場している。
浮世絵に描かれた浴衣、今回あらためて見てみると、
あえて平面的に描かれている顔と対比して、細かく立体的に描かれている。
特に、絞りの表現は布の表面の凹凸が浮き立ってくるようだ。
江戸名所百人美女-薬げんぼり-768x1111-708x1024.jpg)
歌川国貞(三代豊国) 江戸名所百人美女 薬げんぼり 安政5年(1858)3月
大きなタコの絵柄が目をひく本作だが、そもそもタイトルになっている「薬げんぼり」とはなんだろうか。
(おそらく、展示の解説に書かれていたかもしれないが、読み逃してしまった)
薬げんぼりとは、薬研掘(やげんぼり)という現在の東日本橋付近にあった運河のこと。
その名称は、薬研という漢方薬を粉砕する道具の形に似ていることに由来するようだ。
太田記念美術館のtwitterによれば、
『部屋着や夏の散歩時、風呂あがりの身ぬぐいとして着用された浴衣。
大柄が用いられることもあり、本図では大きな蛸の模様が目を引きます。』とある。
いわば、江戸時代のバスローブといったところ。
青と群青地の浴衣から、ちらりと見える赤い湯文字(ゆもじ)がいい。
匂いたつ色香は、現代のバスローブでは遠く及ばない域にある。
1階をひととおり見終わってみると、いいなと思ったのは歌川国貞の浮世絵ばかりだった。
連れの友人にそう話すと、友人のお気に入りはまったく違う。
アタリマエだけど、人それぞれの「好き」があるということだよね。
2階への階段をあがり、ちらしに使われていた作品の前にくる。
実際には3枚組の作品であること、まったく知らず。
手にした着物の裾が揺れ、燕の描かれた団扇が風を送り、右端の美女が今にも歩き出しそうな構成だ。
-十二月ノ内-水無月-土用干-1024x482.jpg)
歌川国貞(三代豊国) 十二月ノ内 水無月 土用干 安政元年(1854)4月
中央の美女の浴衣に大胆に描かれた 源氏香文様(げんじこうもんよう)がなんとも粋である。
この浴衣を着こなすには、相当の女子力の高さが必要だろう。
中央手前にある西瓜が、またなんとも美味しそうだ。
こんな風に角切りにしていただく食べ方もあるんだな。
西瓜を盛り付けた器は、このために作られたかのように、ぴったりとおさまっている。
ちなみに、歌舞伎座資料館で公開されている『江戸文化食紀行 -江戸の美味探訪- NO.16 西瓜』によると、この当時の西瓜は現在のような十分な甘さはなかったとのこと。
ぞれでも、描かれた西瓜は実に美味しそうなのだ。

歌川広重 東海道五拾三次之内 鳴海 名物有松絞 天保4年(1833)頃
国貞ばかり紹介してきたが、こちらは広重。
ヒロシゲブルーとも呼ばれる青の世界は、唯一無二のものに思える。
繊細な筆遣いで描く江戸庶民の様子は、その時代にタイムスリップしたかのようなリアリティを持って、みるものに訴えかけてくる。
展覧会では、このほかにも多くの作品が展示されている。
特に本展覧会のメインテーマの一つである、青の変遷、
ベルリンブルーの登場により、どのように浮世絵の青の表現が変化していったか
ぜひ実際に足を運んで、直接確かめていただきたいと思う。