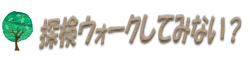到達:2025年3月
難易度:■■□□(初級)
港から菅島灯台(すがしまとうだい、三重県鳥羽市)への行きは順調だった。だが、帰りは道を間違えたり、どっちに曲がるか迷ったりしているうちに、船の時刻が迫って大汗をかいた。雨が降っていたので、中も外も濡れまくり、となってしまった。
伊勢志摩で著名な灯台と言えば、なんといっても菅島灯台だろう。日本の「灯台の父」ブラントンが設計したというだけでなく、ほかにはないユニークな形状が非常に特徴的だ。

神島灯台(三重県鳥羽市、1910年初点灯)と伊良湖岬灯台(愛知県田原市、1929年初点灯)は、伊良湖水道を両側から照らしている。それに対し、菅島灯台は太平洋(遠州灘)を照らしている。初点灯1873年(明治6年)という早い時期につくられたのも、諸外国の船が九州や近畿から東京に向かうのに必要だと見なされたからだろう。
菅島灯台のある菅島へは、神島(神島灯台)や答志島(島ヶ埼灯台)と同じく、佐田浜(鳥羽マリンターミナル)から鳥羽市営定期船で向かう。
灯台は、港から山を越えた島の反対側にある。ルートは2通り。島の北にある白鬚神社近くを通るルート(地図ではオレンジ線)と、住宅地の中をのぼっていくルート(地図では青線)だ。

青線ルートの方が距離が短いと思うのだが、先人はみなさんオレンジ線ルートを通っている。なぜだろう。近畿自然歩道として指定されているからかな。
どちらのルートも、何カ所か分岐があるが、しっかりした道標があるので迷うことはない。……はずが、帰り道ではけっこうオロオロしてしまった。なぜかは後述する。
菅島に行ったのは、午前中に答志島の島ヶ埼灯台に行ったあとの午後。いったん鳥羽マリンターミナルに戻り、もう一度鳥羽市営定期船に乗る。弱い雨は降り続いている。

15分弱で菅島に到着。大きな存在感を持つ、港の正面の建物は菅島小学校だ(別の日に撮影した写真なので天気が違う)。校舎の中央に、菅島灯台を模した塔がある。灯台が島のシンボルになっているということか。

船を降りて上下のレインウェア(カッパ)を着込む。港から左方向に向かって、この植え込みの向こう側を左に曲がる。

少し先、ここで右に曲がる。郵便局に行く道だ。

住宅が密集する細い道を進む。

少し歩くと、住宅がなくなり、山道に差しかかった。

次第に勾配がきつくなるが、足元はコンクリートで舗装されているから、息は苦しいものの、歩きにくくはない。

今回行った菅島灯台、神島灯台、島ヶ埼灯台(答志島)という鳥羽周辺の灯台のうち、この菅島灯台と神島灯台は、道がほとんどコンクリート舗装されていた。観光資源として考えられている、ということだな。
そこそこ長くてきつい道をのぼり切ると、最初の分岐があった。

左に「菅島灯台」と書かれているので迷いはない。ただ、「おんま浜」が指すような、左斜め前に向かう道っぽいものはないように見える。今来た道の行き先は「菅島漁港」。
下り坂を進むと次に現れるのがこの分岐だ。ここも迷いはない。

「監的哨」はおそらく監視所のような軍の施設だ。このあたりの最高点(100.9m)付近にあるのだろう。
ちなみに、菅島の最高点は、さっき道標にあった「大山山頂」で236.4m。その南西側は採石場になっていて、航空写真を見るとだいぶ無惨な感じの山肌になっている。
そしてまたもや分岐。

左の道を少し行って、道標を確かめる。灯台はこの分岐を右だ。

今来た道の行き先は「菅島漁港」ではなく「おんま浜」になっている。帰るときに覚えておこう。
さらに分岐。道標の下に別の案内もあるから、間違いようはない。

しかし、ここにバイクを置きっぱなしってどうゆうこと?
そしてすぐ先に菅島灯台があった。港から15分ちょっとと、予想より早く着いた。一面の水仙は自生らしい。

初点灯は1873年(明治6年)。それにしてもこんな太い灯塔は見たことがない。ブラントン設計なのに得意の半円形付属舎がないし、レンガ造だし、灯籠の形もいわゆる「ブラントン式」ではない、非常にユニークな形状だ。ちょっと微笑ましい感じ。
こういう形になった理由は、この記事で不動まゆうさんが推測されている。

手前の区画は、退息所(官舎)があった場所だろう。きれいに整備されているのを見ると、地元で大切にされているんだな、と感じる。
近代化産業遺産、登録有形文化財、重要文化財といろいろな指定を受けているためか、光源をLEDにするときも気を使って、ちょっと離れた場所にソーラーパネルを設置したという。次の写真の左端のものがそれらしい。

明治時代の石造の壁面は味わい深いが、レンガ造もそれとはまた少し違う魅力がある。
いつも訪れている灯台に比べると、手入れがされすぎている面はあるけど、ゆったりできる空間だ。この太さのせいかな。これで天気がよくて海がきれいならよかったのだが。
帰りの船の時刻まであと45分。だいぶ余裕があるので、来たときの道よりは少し距離がある、もう一つのルートで港まで戻ることにした(次に再掲する地図のオレンジ線)。

少し戻った最初の分岐で、灯台でない方に行くと、かなり急な下り坂だ。階段の模様がしゃれている。

4~5分くだったあたりで右手に海岸が見えてきた。これはおかしい! もし海岸が見えるとすればそれは「しろんご浜」で、こんなに右に見えることはないはずだ。
この段階になって、あわててスマホのGPSをオンにすると、灯台のすぐ下あたりにいることがわかった。道を間違えたのだ。
坂をのぼり直すのはきついが、仕方ない。
さっきの分岐まで戻り、道標を確かめると、向かっていたのは「菅谷浜 200m」とあった。

菅谷浜がどこかはわからないが、距離200mは近すぎる。前掲の地図にこの分岐と菅谷浜の場所を推測で書き入れたが、もう一つ先の分岐を曲がらなければいけなかったのだ。これで10分近い時間と、けっこうな体力をロスした。

そうそう、ここを「白鬚神社 600m」の方だ。……と思う。ところで行きに来た方向が「おんま浜 750m」とあるが、おんま浜ってどこだ?
事前に見た国土地理院の地図にもGoogleマップにも、菅谷浜、おんま浜、しろんご浜などの地名の記載がなかったので、島のどのあたりにあるのかがわからない。道標が整備されているのはありがたいのだが、書かれた地名では行くべき道なのかどうかが判断できない、という落とし穴があった。
ということで、多少の不安を持ちながら、白鬚神社方向に歩き出す。時間をロスしたので少し急ぎ足になる。
ところが、上下のレインウェアを着込んでいるので、上昇した体温が発散せず汗をかいてきた。かといって、雨降りの中で上着を脱ごうとすると雨に濡れてしまう。雨宿りできるところなどない。
10分ほど歩いてどうにも暑さがガマンできなくなってきたころに、あった! 道から少し階段をあがったところにあずまやがあったのだ。なんと都合がいいことか。展望台と休憩所を兼ねているようで、灯台も頭だけ見える。

無事上着(コート)を脱げたのはいいが、リュックサックには入りきらないので、胴に巻きつけ、再びレインウェアを着る。ちょっと急がねば。
傘をさしながら、スマホで現在地を確かめながら、巻き付けた上着が落ちないようにしながら、ときどきカメラを構えながら、急いで歩くのは難しい。外側は雨で、内側は汗で、どっちもびっしょりだ。
また分岐に来た。右上から歩いてきた。

これまで白鬚神社を目指してきたので、「白鬚神社 100m」が指す左下に向かいそうになるが、そうではない。「菅島漁港 1.5km」が指す後ろ方向の道に行くべきなのだ。
そしてすぐ次の分岐。あわてていたのでブレまくっている写真しかない。右上から来て、後ろ方向に行くべきなのだが、左下の「しろんご浜」に行くべきなのか、一瞬迷う。

道が海岸線に対してどのあたりを通っていて、道の分岐地点、白鬚神社、しろんご浜の位置関係がどうなっているか、よくわからないのだ。国土地理院の地図なら道が描かれているのだが、現在地がGPSでわかるGoogleマップはこのあたりの道の表記がないから、正しい道を歩いているという確信が今ひとつ持てない。
このルート、道標がきちんと立っているのが事前にわかっていたので、あまり地図を詳しく見ていなかったのが悔やまれる。
少し歩いたところに道標があった。道はあっているが、まだ1.3kmもある(漁港と連絡船桟橋が近くだとして)。船の時刻まであと25分。時速4kmで歩くと20分だから、なんとか間に合うというレベルだ。

道は舗装されているし、広いし、傾斜は急じゃない。せめて傘をささないで済めば片手が空くのに。

最後の分岐から10分弱、ようやく港が見えた。

そして海べりにたどり着いた。といっても桟橋までまだ700m以上あるのだが。

桟橋(橋の下あたりにある)が見えてきた。

早足で歩いたおかげで、船の時刻の10分前に無事到着。
灯台を出る時点で「だいぶ余裕がある」と思ったのに、予想外の慌ただしさで(冷や)汗をかいた。やっぱり、通るかもしれないルートは、十分に地形などを頭に入れておかないといけないな。