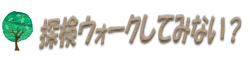コンテンツ
観音埼灯台(かんのんさきとうだい)は、三浦半島東端の観音崎にたつ八角形の灯台だ。東京湾の入り口に位置するこの灯台は、1869年(明治2年)に初めて点灯されてから150年以上、周囲の海を照らし続ける日本最古の洋式灯台でもある。
映画「喜びも悲しみも幾歳月」にも登場

1957年(昭和32年)に公開された「喜びも悲しみも幾年月(いくとしつき)」は、灯台守夫婦の実直な半生を描いたものだが、観音埼灯台は最初の赴任地であり戦時中における灯台をとりまく様々な情勢を映画を通して知ることができる。
上の写真と下の写真は両方とも映画の中の1シーンだが、冒頭に掲げた現在の観音埼灯台と同じ灯台のようにみえるので、本当の灯台を一部使ってロケが行われたようだ。
65年前の灯台の生の映像をみることができるという点も、この映画の鑑賞ポイントの一つである。

激動の時代に建てられた観音埼灯台

Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
映画に登場した観音埼灯台は実は3代目である。やや不鮮明であるが、上の写真は初代の灯台で、四角い洋館の上にレンガ造りの灯塔が設けられていた。
設計したのはフランス人技師のフランソワ・レオンス・ヴェルニー(François Léonce Verny)である。
ペリーの黒船が浦賀に来航したのが1853年(嘉永6年)。その後、幕末の激動の中、イギリス・アメリカ・フランス・オランダの4か国と関税に関する条約(「改税約書」:江戸条約とも呼ばれる)が結ばれた。
日本の西洋式灯台建設にかかわる先駆者の一人、工学博士の石橋絢彦氏は、大正6年に刊行された工学会誌の中で以下のように書いている。(※一部現代かなづかいに修正)
日本政府は灯明台、浮木、瀬印木を建つへきの項あり(江戸条約第11条 日本政府ハ外国貿易ノタメ開キタル各港最寄船ノ出入ノ安全ノタメ灯明台、浮木、瀬印木ヲ備フベシ) 9月四国公使は灯明台八所(劍埼、観音塔、野島埼、神子元島、樫野埼、汐岬、佐多岬、伊王島) 燈明船二所(本牧、函館)を建設されんことを請ふ
石橋絢彦氏、「日本航路標識沿革」『工学会誌 第405巻』
つまりは、開国に従い、外国船の安全航行のため急遽本格的な灯台を建てなければいけなくなったということで、浦賀水道と東京湾を照らす観音埼灯台もその1つであったというわけだ。
さらに、英国に託した技師の到着を待つ時間もなく、横須賀製鉄所建造のために来日していたヴェルニーに観音埼をはじめとする4つの灯台建設を依頼したとある。実際には、ヴェルニーの命で助手のフロランが観音埼灯台の建設に注力した。
こうした背景でこの当時、次々と西洋式灯台が建てられていったが、一番最初に完成したのが観音埼灯台であり、冒頭でも述べたように、日本最初の西洋式灯台という位置づけなのである。
絵師の描く観音埼灯台
前回の記事で、葛飾北斎や歌川広重が描いた浦賀の風景の中に、和式灯台である「燈明堂」が描きこまれていたという話をした。
江戸時代から浦賀の海を照らし続けた燈明台が役目を終えたのは、観音埼灯台が建設されたからである。当時の最高技術の洋式灯台と比べてしまえば、機能的な見劣りはいかんともしがたく、廃止になったのも致し方ないことなのだろう。
実は明治時代の版画家「小林清親(きよちか)」が、この初代の観音埼灯台を描いている。記録によれば描かれたのは1897年(明治30年)、灯台に明かりが灯されてから約30年後の姿である。現存しているモノクロの初代の写真と見比べても、忠実にその姿が再現されていることがわかる。

Kobayashi Kiyochika, Public domain, via Wikimedia Commons
ひとつ面白いのは、洋館の屋根の上にあるレンガ造りの灯塔がレンガ色で表現されていることだ。徹底的に調べていないので不確かな情報ではあるが、この部分は白く塗られていたと聞く。白く塗られていない時期があったのか、あるいは絵を描く際に現物を間近にみておらず「煉瓦」という情報でレンガ色に彩色されたのか、そのあたりははっきりとはわからない。
観音崎は比較的近い場所にあるにもかかわらず、訪問したことがない。近くにレンガ造りの砲台遺構があるようなので、遠くない時期に行きたいなーと思う。
※参考資料
石橋絢彦氏、「日本航路標識沿革」『工学会誌 第405巻』 294p