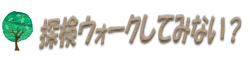まだ年が明けて間もない、世間の動きがお正月モード全開の頃に、東京西部にある狭山湖と多摩湖に行ってきた。
以前から美しいと評判の取水塔を写真に撮りたかったからだ。
幸い天気もよく、煌めく湖面に目をほそめつつ、まるで北欧の昔話にでてくるような取水塔の写真を撮ることができた。なにより、小さい頃何度も歌ったあの「多摩湖」のほとりに立てたことに、ささやかな感動もあった。
正月休みが明け、そのプチ感動を同僚に伝えようとしたが、アラサーの同僚は東村山音頭など知るはずもない。「ひがしむらやーまー、にわさーきゃたまぁこー」と歌い軽く踊って見せたが、苦笑されただけでその場は終わった。
その後、わずか3か月もたたないうちに、志村けんさんは亡くなってしまった。ご病気であるということが報道されており、お若く見えても70歳、万が一ということも考えないではなかったが、実際の訃報を耳にした時、思わず叫び声がでた。
正直なところ、今現在大ファンというわけでもなかったし、大人になってからはほとんど冠番組も見ていなかった。他の多くの著名人がなくなったときと同じように、驚きつつもほどなく日常に戻る・・はずだったのに、断続的に涙が流れてとまらなくなってしまった。
「悲しい」という感情を感じる以前に、涙が次から次へと流れ出てくる。その状態が、半日も続いただろうか。なぜ自分はこんなに泣いているのだろう?と冷静なもう1人の自分が俯瞰で涙を流す自分を眺めている、そんな感覚だった。
日本全体を悲しみの渦に巻き込んだ志村けんさんの訃報から1か月、今日、高井浩章さんという方のコラムを読んだ。
志村けんさんの死が、なぜ自分にとってキツいのか、考えた ハフポストより
この文章を読んで、うまく表現できないでいた自身の涙の理由の1つが、すとんと腑に落ちたような気がした。この方がおっしゃるように、志村けんさんが亡くなったということは、それと同時に、共有した体験や文化といった目に見えない荷物が、走り続けている列車から転げ落ち、その場所からどんどん離れていくような、そんな喪失感を感じてしまったからなのかもしれない。
当たり前のことなのだけれど、失ってみなければわからないもの
というのがあるのだと、この年になって改めて思い知らされたのだ。
志村けんさんのご冥福と、感謝と、平穏な世界の回復を祈って。