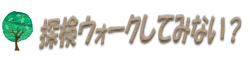1995年(平成7年)、国道401号に架橋された尾瀬大橋(群馬県片品村)は、尾瀬国立公園への玄関口でもある。尾瀬大橋の主塔と橋脚は、水芭蕉をイメージしたデザインとなっている。
この優美な姿の斜張橋は、人工建造物でありながら周辺の景色に溶け込むように、自然な姿で訪れるものを出迎えてくれる。
尾瀬へのアプローチは、この橋から

上の写真では、尾瀬大橋の主塔と一体になった橋脚の上部が見える。中央部が膨らみ下方にしぼんでいく曲線は、まさに水芭蕉の姿を思い起こさせる。

橋長は230m、2径間連続PC斜張橋で、主塔構造を「1室箱桁断面」することで斜材張力による「ねじれ」外力が作用しないよう設計されているとのこと。



なお、コチラの動画では、さまざまな角度から尾瀬大橋の全体像を確認できる(群馬県建設企画課 公開)。
尾瀬大橋から眺める大滝調整池
この記事の冒頭にある尾瀬大橋の写真は、道の駅「尾瀬かたしな」のテラスから撮影したものだ。上の写真は、それとは逆に、尾瀬大橋から尾瀬かたしな方向を撮影している。注目していただきたいのは、中央に写る水門のようにみえる建造物である。
わかりやすいように、その場所を拡大してみよう。
尾瀬大橋が架橋されている場所の地図をみると一目瞭然なのだが、大滝川の流れはこの場所でいったんせき止められ、調整池(大滝調整池)となっている。大滝調整池の西側には、ダムのように水をせき止める堰(せき)があり、片品川に放出して発電に利用する。
ちなみに、役割的にはダムと同じように思えるが、この堰は高さが11mで河川法上のダムに該当しないため(ダムは15m以上)、小規模なダムを表す堰堤(えんてい)という言葉を使い、大滝堰堤と呼ばれることもある。

取水堰のある方向とは逆の東方向を臨む。通常の水位がどの程度かわからないが、今はかなり貯水の少ない状態ではないだろうか。
しかし、こうした水位変動がある場所で生育している植物たちをみると、なんともたくましいものだなと思う。