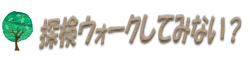到達:2025年3月
難易度:■■■□(中級)
島ヶ埼灯台(しまがさきとうだい、三重県鳥羽市)へは、「道がよくわからないかもしれない」というところが何カ所かありそうだ、と事前に予想していたが、行ってみたらそうでもなかった。
1カ所、倒れている道標の世話になったが、あとはわりと道がはっきりしていたし、危ないところもない。しかも、いまでも継続して道が整備されているようだ。
島ヶ埼灯台への行程は、山道を長めに歩く、ということにつきる。これで雨が降っていなければ、もう少し気持ちよかったのだが…。
今回、鳥羽を起点にして、離島にある3つの灯台(島ヶ埼灯台、神島灯台、菅島灯台)と伊良湖岬灯台に行った。ほかの3つの灯台は広い遠州灘(太平洋)に面しているのだが、島ヶ埼灯台だけはちょっと違い、鳥羽周辺の狭い海域のためのもののようだ。

島ヶ埼灯台は、この海域では一番大きい答志島(とうしじま)の西端にあり、桃取(ももとり)という港から向かう。答志島にはほかに答志、和具(わぐ)、というあわせて3つの港があり、それぞれ佐田浜(鳥羽マリンターミナル)から鳥羽市営定期船が出ている。
島ヶ埼灯台は鳥羽マリンターミナルからも見える。島が重なって写っているのでわかりにくいが、桃取行きの船は灯台の左を通って、島の向こう側に向かう。

ただし、上の写真は別の日に撮ったもの。実際に行ったのはしとしと小雨が降る日だった。

船は灯台のある岬(島ヶ埼)を回り込み、島の北側に向かう。こちら側には桟橋と急な階段があるが、使われていないように見える。高い鉄塔は、鳥羽本土からの送電線のためのもの。

鳥羽マリンターミナルから10分少しで答志島桃取に到着。左端に連絡船待合所が小さく見えている。右端の建物が、灯台へののぼり口がある桃取小学校跡。

灯台までのルートは次のとおり(青線)。地図上の道と違うところは大まかな推測だけど。

割と広い連絡船待合所で上下のレインウェアを着込み、傘をさして出発。足元は最初からレインシューズ。この先を右に行く。

港に沿う形で歩いていくと、桃取小学校跡に着く。廃校のはずだが何カ所かに室内灯がついていて子供の声も聞こえる。保育所として使われているようだ。

門に入らず手前を左に行く。道というより通路という感じ。

そして“校舎の裏側”。道ではないね。

しばらく進むと、「学校の敷地ではないよ」という柵があり、いかにも左へ行きなさい、という感じになる。

はっきりした道ではないので、多少自信が持てないが、左にある廃小屋の左を抜けると、道っぽいものが続いている。

どうやらこれであっているようだ。

「学校の裏手に回って、途中から山道に入る」のような情報を事前に見たときは、この情報だけだとちょっと迷うかも、という不安があった。しかし、実際に行ってみると「ああ、こういうことだな」と納得した。
このあとは普通の山道だ。季節柄、草もないので道はわかりやすい。

しばらく行くと、道はつづら折りになる。傾斜は結構急で、一部は木の階段が設けられている。

先人のみなさんの記事には、「朽ちた木製の階段」「腐って崩れている」という表現がある。しかし、いまはかなりしっかりしているし、木がかなり新しいところを見ると、ごく近年、階段が作り直されたようだ。
つづら折りを4、5回繰り返すと、のぼり道は終わる。地面には「空気弁 上水道」と書かれたふたがある。後述するように、この下を上水道が通っているんだろう。

国土地理院の地図では、ここから左右に道が分かれている。道だとはっきりわかるのは、左ののぼり階段だけだ。こちらへは行かず、直進する。そもそもこのあたりから灯台まで、国土地理院の地図に書かれている歩道は、現状とちょっと違うところが多かった(よくあることだ、仕方ない)。

ここから少しくだっていくと、いきなり大きなタンクが現れた。港から15分ぐらい。

タンクには「第1配水池」とあり、島の上水道用水を蓄えるもののようだ。離島の水道事情はよく知らないが、これは鳥羽の本土側から海底送水管で送られた水を貯めておくということか?
このタンクは、Googleマップや国土地理院の地図などの航空写真でもはっきり写っている。以下に再掲する国土地理院の地図にも赤い丸が描かれている(②の指す場所)。こんな施設、ほかの島にもあったかなあ?

帰りに気づいたのだが、タンクのある敷地から、桃取小学校跡あたりに向かうコンクリートの階段があった。これまで歩いてきた道とは別に、タンクの点検用の道を作ったのか?

灯台クエスト続行。タンクを通りすぎ、さらにくだっていく。

壊れているところはあるものの、わりと新しめの手すりが続いている。さっきの木製階段といい、この整備状況、灯台に行くもの好きのためだけなのだろうか。それにしては手がかかっているのだが。

道が直進と右に分かれている場所に来た(地図の③あたり)。先人のみなさんによると、ここに道標があるはずだが…。

あった。支柱が折れて倒れていたのだ。よく見れば、上の写真にも写っている。

そして「島ヶ埼灯台」を指す方向は、倒れても正しくなっている。直進ではなく、右に向かうのだ。だれかが配慮して、道標をこのように置いてくれたのか。確かにここは道標がないと直進してしまいそうだ。
上記の写真では右に道があるかどうかわかりにくいが、その場に行けば道は判別できるから心配ない。国土地理院の地図には描かれていない道と思われる。

その後、道は小高い場所の左を巻くような形で進む。

すると、木が伐採され、森がなくなっている場所に出た(地図の④あたり)。建物のためとも思える平らな区画がある。道の一部分には、崩れたりぬかるんだりしないための敷物もある。

ここに木が伐採された区画があることは、Googleマップの航空写真(2025年3月現在)で確認できる。国土地理院地図(2020年撮影)では見当たらないので、この数年で行われた工事だということだ。こんな人里から離れ、アクセスの悪いところになにをつくるつもりなんだろう。
左カーブを進むと、ついに鉄塔が見えてきた。本土側から答志島に電力を送る送電線の鉄塔で、圧倒的な高さだ。

道は木の階段ののぼりくだりを経て、鉄塔の下に続いている(地図の⑤あたり)。鉄塔の脚の間、電柱のすぐ左に、灯台の頭が見えているのがわかるだろうか。

さっきと同様の敷物が「ここを通りなよ」と敷かれている。鉄塔の前後には、木の幹や枝を短く切ったものが積まれている。ここも2020年の写真では森だった。伐採した理由はわからない。
いよいよ灯台に近づいてきたが(電柱の左)、木に隠れて塔頂しか見えない。

最後のアプローチには柵があるほか、海を眺めるためのベンチもある。

ただ、ベンチを作ったころより草木が成長したようで、座ると海が見えなくなる。しかも小雨が降るような天気なので、残念ながら眺望もよくなかった。

ようやく島ヶ埼灯台に到着。配水タンクから15分ぐらい、港からだと30分ぐらいの道のりだった。

灯塔を上から見るとおそらく「×」というかなり珍しい形だ。さらに塔頂は七角形というべきか、灯塔とはズレた形になっている。ずいぶんと気合いを入れた設計をしたものだ。

銘板も海上保安庁の案内板もないのではっきりしないが、初点灯は1957年(昭和32年)のようだ。神島灯台や菅島灯台が明治時代につくられたのに対し、島ヶ埼灯台の時代が違うのは、対応する海域が違うからだろうな。
敷地が狭いこともあり、木にじゃまされずに灯台の全体像を撮ることができない。樹木が伸び、年月を経るとともに姿が見えづらくなったんだろう。かといって、鉄塔付近のように森を丸裸にされてしまうのもどうかと思う。「全体像が見えない灯台」というのも悪くないかもしれない。
帰りは同じ道を戻ったのだが、前述したように、配水タンクのところで、コンクリートの階段を見つけた。ここをおりてみることも考えたのだが、途中で通行できなかったり、へんな海岸に出てしまったりする危険性もあるので、やめておいた。

ただ、この地図によれば、②の配水タンクから①の桃取小学校跡の校庭脇、およびその西寄りにおりていく道がある。この道が実際に通れる可能性もある。
ということで、来たのと同じ道を桃取小学校跡まで戻り、校庭の反対側に回ってみることにした。

校庭のすぐ脇の道を山の方に進むと、いくつかの住宅の先で行き止まりのようだった(×印)。
さらに西側、海岸近くまで行って小屋の横を抜けると、山方向に向かう道があった。

これはもしかしたら配水タンクまで通じているかも!? ただ、仮に通じていたとしても、そこまでのぼって確認する元気はすでになく、今回のクエストはここで終了することにした。

反対側の海岸は、えらくきれいなビーチだった。子供用のプール、シャワーやトイレのある建物など、とてもカネがかかった感じの場所だ。さすがにこの季節、この天気なのでだれもいなかったが。
鉄道駅から30分で来られるビーチ。穴場かもしれない。